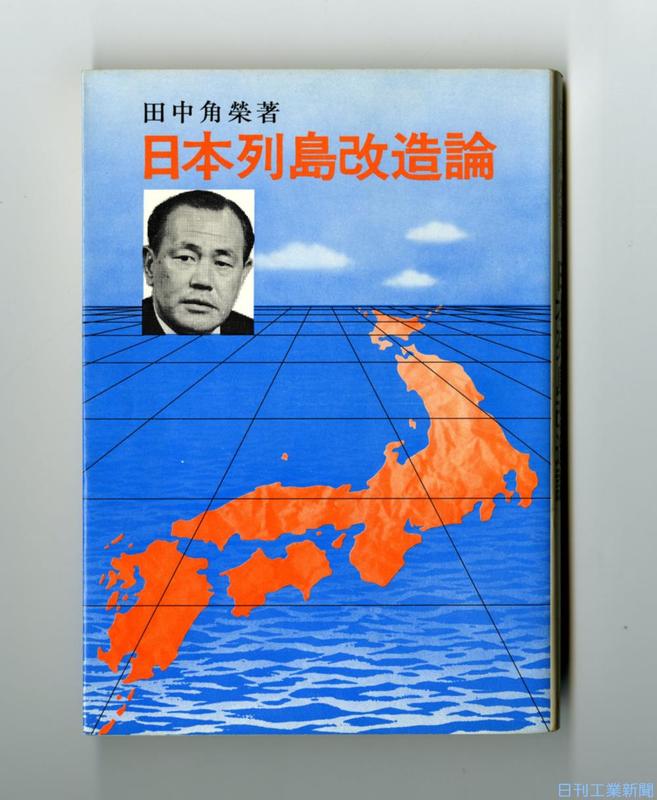父・田中角栄が娘に送った人生最高のスピーチ
「父と私」(田中 眞紀子著)の一節より
政治家という職業は、後援会でのミニ集会をはじめとして、国会での質疑応答や街頭演説など公の場でスピーチをする機会が多い。
“演説力は政治家の命”と言われる所以である。
私も企業など諸団体の会合や大学での講義など、千人規模のハコもの(構造物の中でのスピーチを業界用語でこう呼ぶ)をこなしたことも数多くある。
また、選挙応援で宣伝カーの上で両手に持ちきれないほどの数のマイクを握りしめて、それこそ足を踏ん張って、ズラリと居並ぶマスコミのカメラの放列の前で不特定多数の聴衆に向かって街頭演説をした経験も多い。そのほかに冠婚葬祭や各種式典など決まりきった場での急なご指名もこなしてきた。
今振り返ってみるに、生涯忘れられないスピーチがいくつかある。そのなかの一つに、私の結婚式でこともあろうに突然父が自ら進んで行ったものがある。
昭和44(1969)年4月。当時、日本鋼管(現JFEホールディングス)社員であった新郎鈴木直紀氏は弱冠28歳。官僚の家庭の三男坊としてのんびりと暮らしていた模様であった。
お互いの家族は親族が少なかったこともあり、都内のホテルで静かで落ち着いた雰囲気のなかで神前結婚式を挙げた。引き続き行われた披露宴は、着席形式で小規模なものを私たちは希望していたのだが、当時の父の社会的な立場もあって政財官界からの多数の出席者に配慮して立食形式となった。
時間を有効に使うということは父の人生の重要なモットーの一つであり、自分の時間はもちろんのこと、他人をむやみに長時間拘束するべきではないというのが持論であった。
着席形式でお客様が時間を気にしてモジモジしたり、時計をチラチラ見るようなことになっては申し訳ないという考え方であった。したがって、婚礼といえども客人同士が自由に交流し、軽い飲食後にはサッと退出できるということに父は強くこだわっていた。
そんな大宴会も終わりに近づいた頃、司会者にちょっと手を挙げてから、突然父がマイクの前にスタスタと歩み出た。いったい何事かとざわめく人々の前で父は恭しく来賓の方々へ頭を下げてからこう切り出した。
「花嫁の父がスピーチをするなどということは異例であることは充分心得ております。しかし、眞紀子の父親としてどうしても直紀君に言っておきたいことがあります」と述べた。
“これはいったいなんたること!いったい全体何を言い出すやら……”と、文金高島田に白無垢、打掛姿の私は大いに動揺した。
「私たち夫婦には正法(まさのり)という長男がおりましたが、仏法の名前負けをしたのか、幼くして肺炎で亡くなりました。眞紀子という名前は訓読みをすると『まさのり子』となります。年子の兄妹はとても仲良しで、まるで双子のようにして育ちました。正法の死は今も私たち夫婦にとって痛恨の極みであります。長男の死後は、眞紀子をあえて女の子というよりも、田中家の跡取りとして男の子のように育ててきました」
「物事の判断を間違えず、どんな時にも責任を取れる人間として教育をしてきたつもりです。その点に関してはいささか自信があります。そこで今後、直紀君が眞紀子に対して料理や掃除など家事一切を普通の女性並みに求めてもらっては困るのであります。そういう教育はまるでしてありません。君が今後、家事などで不満がある時には、ウチの妻君やお手伝いさんをいくらでも派遣します」
この発言に会場はドッとどよめいた。花嫁姿の私は“よりによってこんな時に何を言い出すやら……。失敬な奴め!”と両手をかたく握りしめた。ところが続いて父の口からこんな言葉が飛び出した。
「もう一つだけつけ加えておきます。それはこの子は誰に似たのか大変口が達者であります」
この大真面目な断言口調に人々は遂にゲラゲラと声を出して笑い始めた。
「言わんでいいことをズバリと相手構わず言ってのけます。しかも困ったことにそれが結構的を射ているのであります。しかもさらに続く理屈がこれまた結構理路整然としているので始末が悪い!かくいう私もかなりひどい目にあっている。そこで、今後そういうことがあった場合には遠慮なく殴ってくれて結構です」
ここまで一気に話し終えると父は“ハァ”と一息ついて額の汗をぬぐった。会場はすでに大爆笑の渦である。チラチラと花嫁たる私の反応を観察しながら抱腹絶倒しているお客様もいる。
新郎直紀氏のほうをチラリと見ると、困りきった表情で対応不全といった様子で金屏風の前に立ち尽くしていた。困惑しきった生涯の伴侶となる人物と、熱弁をふるう父との間に立った私は“花嫁姿でさえなければ抗議声明の一つでも発表したいくらいだ”と切歯扼腕した。
「ただし」とさらにつけ加えた。「君は体がでかいから本気でたたかれたらさぞ痛いだろう。殴れとは言ったが、その時は手加減してくれるように頼みます」と言って主人のほうへ向かってお辞儀をしたのである。
世間では権力者と思われていた父のそんな姿に出席者たちは大笑いしながらも、涙ぐんだりして会場には万雷の拍手が鳴り響いた。
“こんなに優しい男性がこんなかわいいお嫁さんを殴るなんてあるはずがないのに”と勝手に得心しつつも、とにかく“神前ではしっかり角隠しをしておいて本当に良かったわい”と内心安堵もした。
ところが次の瞬間、「お転婆娘が今日から私の手を離れると思うと、こんなうれしいことはあ・り・ま・せ・ん……」と言って父はこともあろうに絶句したのである。そんな父の姿に会場のどこかから、「ようし、よくわかった!もういい!角さん、もういいよ!」と声がかかった。
この温かい笑顔と声援に私は胸が熱くなった。父は深々と礼をして、スピーチ未完了のまま自席へ戻り白いハンカチーフで目頭と鼻を拭っていた。この時のスピーチは当時の政財官界でかなり有名な話となった。
母と親交の深かった池田・大平元首相の夫人たちは目白に来られるたびに、「あの時のスピーチを聞いて、田中先生にとって眞紀子ちゃんは掌中の珠。目の中に入れても痛くないとはあのことね」といつも話題にしておられた。
日頃は控えめな母が、「あの親子はいつどこで何を言い出すかわからないところがそっくりなんです。本当に困ったものです」と応じていた。
両親亡き後約22年。今や私たち夫婦には孫たちもいる。この間、主人が私に手をあげたことはただの一度もない。今ではなんとも懐かしく有難いスピーチであったと父に感謝している。
“演説力は政治家の命”と言われる所以である。
私も企業など諸団体の会合や大学での講義など、千人規模のハコもの(構造物の中でのスピーチを業界用語でこう呼ぶ)をこなしたことも数多くある。
また、選挙応援で宣伝カーの上で両手に持ちきれないほどの数のマイクを握りしめて、それこそ足を踏ん張って、ズラリと居並ぶマスコミのカメラの放列の前で不特定多数の聴衆に向かって街頭演説をした経験も多い。そのほかに冠婚葬祭や各種式典など決まりきった場での急なご指名もこなしてきた。
結婚式で突然父が…
今振り返ってみるに、生涯忘れられないスピーチがいくつかある。そのなかの一つに、私の結婚式でこともあろうに突然父が自ら進んで行ったものがある。
昭和44(1969)年4月。当時、日本鋼管(現JFEホールディングス)社員であった新郎鈴木直紀氏は弱冠28歳。官僚の家庭の三男坊としてのんびりと暮らしていた模様であった。
お互いの家族は親族が少なかったこともあり、都内のホテルで静かで落ち着いた雰囲気のなかで神前結婚式を挙げた。引き続き行われた披露宴は、着席形式で小規模なものを私たちは希望していたのだが、当時の父の社会的な立場もあって政財官界からの多数の出席者に配慮して立食形式となった。
時間を有効に使うということは父の人生の重要なモットーの一つであり、自分の時間はもちろんのこと、他人をむやみに長時間拘束するべきではないというのが持論であった。
着席形式でお客様が時間を気にしてモジモジしたり、時計をチラチラ見るようなことになっては申し訳ないという考え方であった。したがって、婚礼といえども客人同士が自由に交流し、軽い飲食後にはサッと退出できるということに父は強くこだわっていた。
そんな大宴会も終わりに近づいた頃、司会者にちょっと手を挙げてから、突然父がマイクの前にスタスタと歩み出た。いったい何事かとざわめく人々の前で父は恭しく来賓の方々へ頭を下げてからこう切り出した。
「花嫁の父がスピーチをするなどということは異例であることは充分心得ております。しかし、眞紀子の父親としてどうしても直紀君に言っておきたいことがあります」と述べた。
“これはいったいなんたること!いったい全体何を言い出すやら……”と、文金高島田に白無垢、打掛姿の私は大いに動揺した。
長男の死と眞紀子の育て方
「私たち夫婦には正法(まさのり)という長男がおりましたが、仏法の名前負けをしたのか、幼くして肺炎で亡くなりました。眞紀子という名前は訓読みをすると『まさのり子』となります。年子の兄妹はとても仲良しで、まるで双子のようにして育ちました。正法の死は今も私たち夫婦にとって痛恨の極みであります。長男の死後は、眞紀子をあえて女の子というよりも、田中家の跡取りとして男の子のように育ててきました」
「物事の判断を間違えず、どんな時にも責任を取れる人間として教育をしてきたつもりです。その点に関してはいささか自信があります。そこで今後、直紀君が眞紀子に対して料理や掃除など家事一切を普通の女性並みに求めてもらっては困るのであります。そういう教育はまるでしてありません。君が今後、家事などで不満がある時には、ウチの妻君やお手伝いさんをいくらでも派遣します」
この発言に会場はドッとどよめいた。花嫁姿の私は“よりによってこんな時に何を言い出すやら……。失敬な奴め!”と両手をかたく握りしめた。ところが続いて父の口からこんな言葉が飛び出した。
「もう一つだけつけ加えておきます。それはこの子は誰に似たのか大変口が達者であります」
この大真面目な断言口調に人々は遂にゲラゲラと声を出して笑い始めた。
「遠慮なく殴ってくれて結構」
「言わんでいいことをズバリと相手構わず言ってのけます。しかも困ったことにそれが結構的を射ているのであります。しかもさらに続く理屈がこれまた結構理路整然としているので始末が悪い!かくいう私もかなりひどい目にあっている。そこで、今後そういうことがあった場合には遠慮なく殴ってくれて結構です」
ここまで一気に話し終えると父は“ハァ”と一息ついて額の汗をぬぐった。会場はすでに大爆笑の渦である。チラチラと花嫁たる私の反応を観察しながら抱腹絶倒しているお客様もいる。
新郎直紀氏のほうをチラリと見ると、困りきった表情で対応不全といった様子で金屏風の前に立ち尽くしていた。困惑しきった生涯の伴侶となる人物と、熱弁をふるう父との間に立った私は“花嫁姿でさえなければ抗議声明の一つでも発表したいくらいだ”と切歯扼腕した。
「ただし」とさらにつけ加えた。「君は体がでかいから本気でたたかれたらさぞ痛いだろう。殴れとは言ったが、その時は手加減してくれるように頼みます」と言って主人のほうへ向かってお辞儀をしたのである。
権力者の姿に会場は万雷の拍手
世間では権力者と思われていた父のそんな姿に出席者たちは大笑いしながらも、涙ぐんだりして会場には万雷の拍手が鳴り響いた。
“こんなに優しい男性がこんなかわいいお嫁さんを殴るなんてあるはずがないのに”と勝手に得心しつつも、とにかく“神前ではしっかり角隠しをしておいて本当に良かったわい”と内心安堵もした。
ところが次の瞬間、「お転婆娘が今日から私の手を離れると思うと、こんなうれしいことはあ・り・ま・せ・ん……」と言って父はこともあろうに絶句したのである。そんな父の姿に会場のどこかから、「ようし、よくわかった!もういい!角さん、もういいよ!」と声がかかった。
この温かい笑顔と声援に私は胸が熱くなった。父は深々と礼をして、スピーチ未完了のまま自席へ戻り白いハンカチーフで目頭と鼻を拭っていた。この時のスピーチは当時の政財官界でかなり有名な話となった。
池田・大平さんたちの記憶
母と親交の深かった池田・大平元首相の夫人たちは目白に来られるたびに、「あの時のスピーチを聞いて、田中先生にとって眞紀子ちゃんは掌中の珠。目の中に入れても痛くないとはあのことね」といつも話題にしておられた。
日頃は控えめな母が、「あの親子はいつどこで何を言い出すかわからないところがそっくりなんです。本当に困ったものです」と応じていた。
両親亡き後約22年。今や私たち夫婦には孫たちもいる。この間、主人が私に手をあげたことはただの一度もない。今ではなんとも懐かしく有難いスピーチであったと父に感謝している。